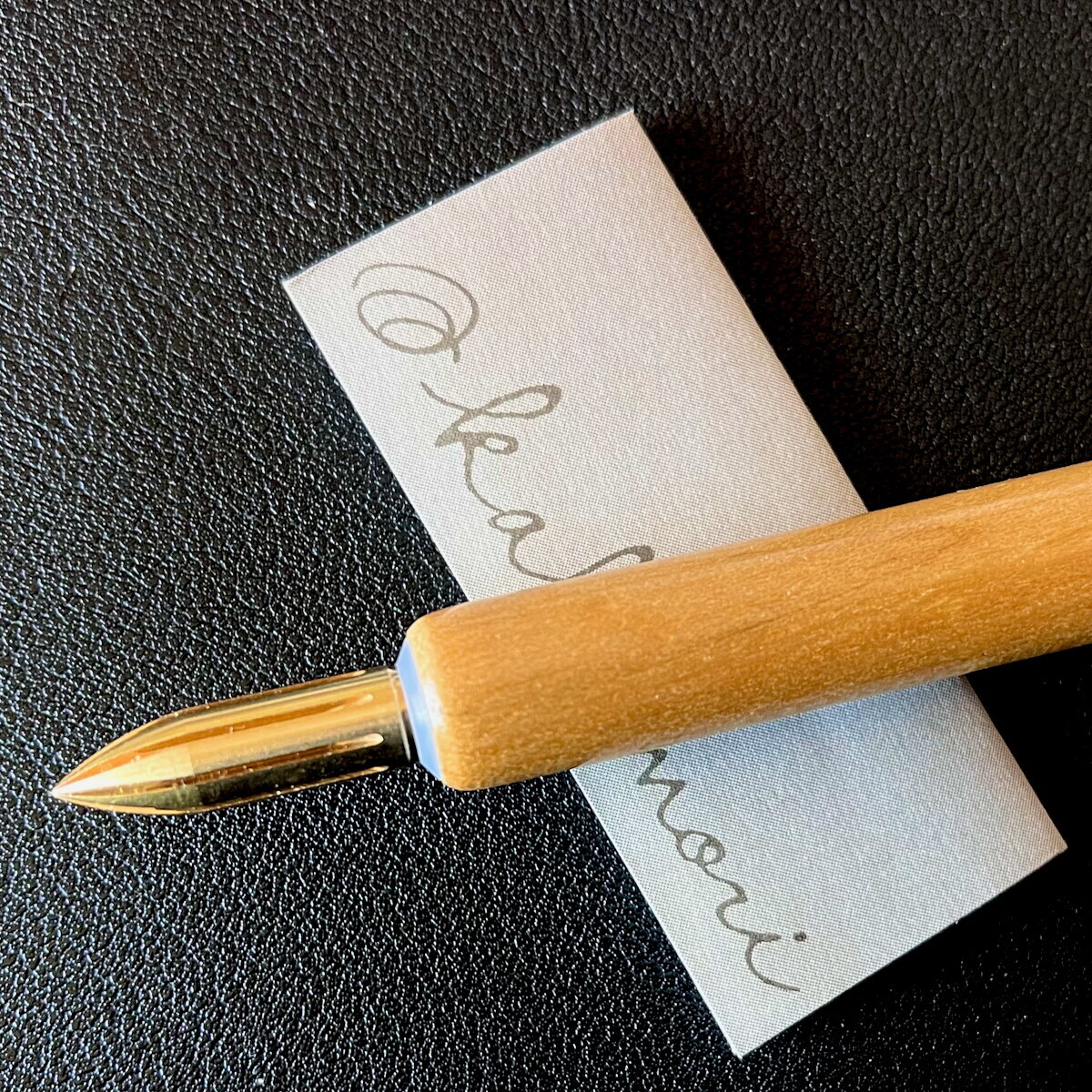↑クリフォード・ブラウンの愛称は「ブラウニー」。
ベニー・ゴルソンが追悼曲として “I Remember Clifford” を作曲して、ジャズのスタンダードナンバーになりました。
1970年代後半にFMラジオのエアチェック(要するにAMより音質のいいFMの音楽番組からラジカセで、カセットテープに録音すること)が流行って、二週間分の(うん?一ヶ月分だった?)FMのラジオ番組表を載せている専門誌が二誌あったんですよね。『FM fan』と『FMレコパル』。その『FMレコパル』にジョージ秋山が漫画でクリフォード・ブラウンの伝記みたいなのを描いたんですよね。その漫画がすごくよくて。すぐにレコードを買ってきて聴きだしたら、これがすごくよかったんだなぁ。ほんとかっこいいぜ。
長浜の駅前にあった「サン・ミュージック」という小さなレコード屋さんで中学生だった僕は友人とお小遣いを貯めてはレコードを買っていたのですが、クリフォード・ブラウンのレコードを眺めていたら、若いお兄さんの店員さんに話しかけられました。「クリフォード・ブラウン聴くの?中学生?中学生でクリフォード・ブラウン?どうしたの?マイルスはもう聴き飽きた?それもいいけどこれもすごくいいよ。おすすめです。」と。僕が手にしていたのはマックスローチとの『 Brown and Roach Incorporated』でしたが、薦められたのは「Clifford Brown Quartet in Paris」でした。
たとえば中学三年生だった1976年はクリフォード・ブラウンが亡くなった1956年から数えて20年後。当時15歳として、生まれる前の1956年は大昔のように思っていましたが、・・・。でも現在、2025年の20年前は2005年ですね。2005年なんてついこないだみたいなものじゃないか。と思えてしまいますが(笑)、15歳の私にとっては、自分が生まれる5年前というのは、ちょっと大昔のような気がしていました。
↑マイルス・デイビスのトランペットを聴いたあとだと、ハードバップの時代はいかにも古臭いジャズのように聴こえるかもしれないけれど、なんだかね、みんな元気だしわりと楽しそうでしょ?クリフォード・ブラウンはスタジオ録音よりライブの録音の方が、僕は演奏が好みだけれど、サービス精神もあるんだなぁ。ソロも短くて一曲の演奏も短い。で、次々曲を演奏していく。もちろん録音機材の問題もあったんだろうけど。

12日(水)
囲碁の棋聖戦を横目でみながら、終日事務仕事。アマゾンで注文したものを忘れていて、拾っていたら、一年間で買った本が次々と出てきたのだが、買ってる割りには読んでない(笑)。棋聖戦、いきなり井山さんのAIの評価値が10%ぐらいだったりしてヒヤヒヤしたけれど、午後に50%と50%の五分五分の評価値になる。素人の私には囲碁界の最高峰の二人が何をやっているのかさっぱりわからないので、AIの評価値がないとなかなか楽しめない。プロ棋士の解説がいつもあるわけでもないし。
13日(木)
一昨日提出した50ページほどの書類だが、昨日、さっそく何ヶ所かミスを指摘されて戻ってきたので、今日はこれから訂正して再提出する予定。世の中、なかなかすんなり順調には進まないぜ(笑)。